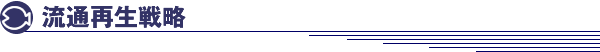B・ウィルソンは『マーチャンダイジング原理』のなかで、「マーチャンダイジングとは、適正な商品を、適正な場所へ、適正な価格で、適正な時期に、適正な方法で、適正な状態において提供するマーケティング戦略である」と定義している。
アメリカ・マーケティング協会(AMA)も同じような定義を行っている。1948年の定義は、「適切な商品を適切な時期に、適切な価格においてマーケティングする計画」とし、1960年代にその定義は、「企業のマーケティング目標を達成するため、特定の商品、サービスを最も役立つ場所と時期と価格と量でマーケティングする計画と管理である」と修正されている。
この定義から、俗にマーチャンダイジングとは、「ファイブ・ライト」(5つのR)と呼ばれた。5つのRとは次の項目である。
- Right Goods (適正な商品)
- Right Time (適正な時期)
- Right Price (適正な価格)
- Right Quantity (適正な量)
- Right Place (適正な場所)
このような定義は、若干抽象的なので、AMAは次のように補足している。つまり「マーチャンダイジングは、主として卸売業、小売業において用いるのであり、製造業の場合はプロダクト・プランニング、またはプロダクト・マネジメントと呼ぶ」と。
三上富三郎教授は『営業の理論』のなかで、「考え方としてマーチャンダイジングは製造業者、販売業者の双方に通じる概念であるが、製造業者はプロダクト・プラニング、販売業者はマーチャンダイジング・セレクションの問題としてその概念を明確にすることが望ましい。すなわち製造業者においては製品計画として、販売業者においては商品選定または仕入政策として用いるが、双方に通じる概念として商品政策という意味に解してよい」としている。つまり、マーチャンダイジングは製造業では製品化計画であり、小売業では商品選定仕入計画であると区別して使用されるべきだと指摘している。
佐藤肇氏は、「メーカーのマーケティング活動におけるマーチャンダイジング(製品計画=商品化計画)」という概念と、商業活動そのものを総称するマーチャンダイジング概念とは厳密に区分して使われなければならない」として、マーチャンダイズには、「商品」という意味と「売買する」という意味があることに着目し、マーチャンダイジングをつぎのように定義している。
「商業の分野においてマーチャンダイジングは、売買するという意味で使われる。つまり、商業者の経済活動の基本的な機能は、販売しようとする商品の選択=品揃えであり、これは仕入れて販売するということであるが、この商品活動の全過程を総称してマーチャンダイジングというのである。」
ここにはじめて「品揃え」という用語が出てきたが、J・W・ウィンゲートは、「マーチャンダイジングとは顧客の需要に即応した商品の品揃えを達成することと、企業成長のため潜在的利益を獲得するための売上、仕入れ、経費のバランスを維持していくこと、広義には商品の仕入活動と販売活動である」と述べている。
このように見てくると、マーチャンダイジングとは、主として小売業者に使用される用語であり、その意味は、適正な品揃えを維持する商品選定にかかわる諸活動と定義することができる。すなわち、サービスしようとする顧客(自社のターゲット顧客あるいは最重要顧客)を理解し、ターゲット顧客、最重要顧客が気に入るような品揃え計画を注意深くたてること、またフリーの顧客のために、その人たちの要求と欲望を最大限に満たすようにいろいろな商品を適切に集める仕事がマーチャンダイジングになる。
| 前の項目 | 小売業は単品管理 |
| 次の項目 | 調達マーチャンダイジングとセレクト・マーチャンダイジング |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。