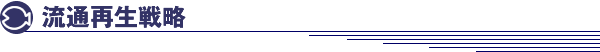第1章 小売業の原点−マーチャンダイジング
小売りの逆選別時代
わずか40年、巨大な小売業者が誕生した。数兆円という巨大な企業である。この成長は、高度経済成長という日本経済の環境と、このチャンスを逃さなかった創業者の先見の明、ほとばしる情熱にあった。しかし、あまりにも急速に戦線が延びた。北海道から沖縄まで店舗網が拡大し、売場が拡大した。いわゆる問屋の成長は、強大化する小売業者にいかに口座を開設してもらうかにかかっている。口座を開設してもらうために家まで建てて上げたという話は稀な話ではない。
そのことが小売業のバイヤーを慢心させてしまった。
これまではもっぱら大量販売という「位置の濫用」によるバイイング活動が主だったといっても過言ではない。「位置の濫用」とは、買手が一方におり、売手が他方にいるシーソーゲームのようなものであり、力にまかせ、買手のほうが動くと、利益は買手のほうに流れるが、売り手のほうは損をする。同様に売り手が力にまかせると、買手側が損をする。この関係は、かけ引きのみが蔓延し、相互不信になる。これを筆者は「リスクのキャッチボール」といった。損を相手に押しつける。条件をのまなければ取引停止にする。仕方なく不利な条件をのむことになる。本来取引とは、かけ引きなどないフェアプレイの精神と誠実に基づくものでなければならない。
大きな組織力にものを言わせた不当な返品、不当な値入率の強要、支払いの延期、不当な契約解除、契約上の義務の回避、拡販費というリベートの強要など悪習の数々、このような不正行為は、実質的には結局ムダが多いことを小売業者は早く理解すべきであった。
| 前の項目 | 調達マーチャンダイジングとセレクト・マーチャンダイジング |
| 次の項目 | 小売りの原点に戻れ |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。