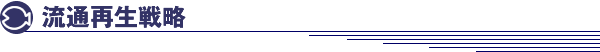最近ポイントカードといってお客様カードを発行するスーパーマーケットが多くなった。しかし、その殆どは顧客データを取っていない。取っていても分析に活用していない。なんのためにカードを発行したのか首を傾げたくなる。間違った導入である。
顧客購買データの代表的な分析方法に、デシル分析という分析手法がある。米国でもヨーロッパでも顧客カードを導入しているスーパーマーケットが共通して分析している手法である。デシルは十分位数、総量を10等分したももの任意の1個の数量。10等分したひとつを分析する統計で用いる手法。購入会員顧客数を総量として、購入金額の高い順に顧客を並べ、顧客総量を10等分する分析手法を、小売業の「デシル分析」としている。
たとえば、あるスーパーマーケットのカード会員購入顧客数(回数ではない)が1万人だったとする。この1万人の購入金額を購入金額順(コンピュータのソートという技術を利用すればたちまち並べ変えてくれる)に並べて上位から10個のグループに分ける。ひとつのグループは1000人ずつグループになる。この1000人ごとの購入金額を合計し、その金額はいくらか、全体売上に占める売上構成比はいくらか、グループごとの顧客一人あたり平均購入金額はいくらかというような集計をし、お客様グループごとの購入動向を理解する分析である。おおむねつぎのような傾向がある。
◆デシル1:全体売上の35%。顧客一人あたり1ヶ月、6万円購入。ほとんどの食料をこの店で購入している固定客、ロイヤルティ(忠実)の高いお客様である。
◆デシル2:全体売上の 20%。デシル1との累計構成比は55%。上位20%のお客様で全売上高の55%になっている。デシル2の1ヶ月顧客単価は3万円。デシル1の半分になっている。ハーフロイヤル(半分の忠実)顧客になる。販促次第ではとても販売チャンスの高いお客様である。
◆デシル3:全体売上の15%。デシル1〜3までの累計構成比は70%。上位30%のお客様で全売上高の70%になっている。デシル3の1ヶ月顧客単価は2万円。デシル1の33%。
◆デシル4 :全体売上の10%。デシル1〜4までの累計構成比は80%。上位40%のお客様で全売上高の80%になっている。デシル4の1ヶ月顧客単価は1万5000円。デシル1の25%。
◆デシル5:全体売上の7%。デシル1〜5までの累計構成比は87%。上位50%のお客様で全売上高のなんと87%になっている。デシル5の1ヶ月顧客単価は1万円。デシル1の17%。
◆デシル6:全体売上の5.5%。デシル1〜6までの累計構成比は92.5%。上位50%のお客様で全売上高の92.5%。デシル6の1ヶ月顧客単価は8000円。デシル1の13%。
◆デシル7:全体売上の4%。デシル1〜7までの累計構成比は96.5%。上位70%のお客様で全売上高の96.5%になっている。デシル7の1ヶ月顧客単価は6000円。デシル1の10%。
◆デシル8:全体売上の2%。デシル1〜8までの累計構成比は98.5%。デシル8の1ヶ月顧客単価は4000円。デシル1の7%。
◆デシル9: 全体売上の0.8%。デシル1〜9までの累計構成比は99.5%。デシル9の1ヶ月顧客単価は1500円。デシル1の3%。
◆デシル10:全体売上の0.5%。デシル1〜10の累計構成比は100%。デシル9の1ヶ月顧客単価は600円。デシル1の1%。
(顧客データ分析やフリークエント・ショッパー・プログラムについては『小売業のためのマーケティング』かんき出版荒川圭基、『挑戦!ロイヤルティ・マーケティング』ジェリコ・コンサルティング荒川圭基、『顧客識別マーケティング』ダイヤモンド社ブライアン・ウォルフなど参照)
| 前の項目 | PI値計算方法の解説 |
| 次の項目 | データマイニングとはなにか |
Copyright 2006 (C) Jericho Consulting Co.,Ltd.
本サイトの全ての文章、画像を無断で転載することを禁じます。